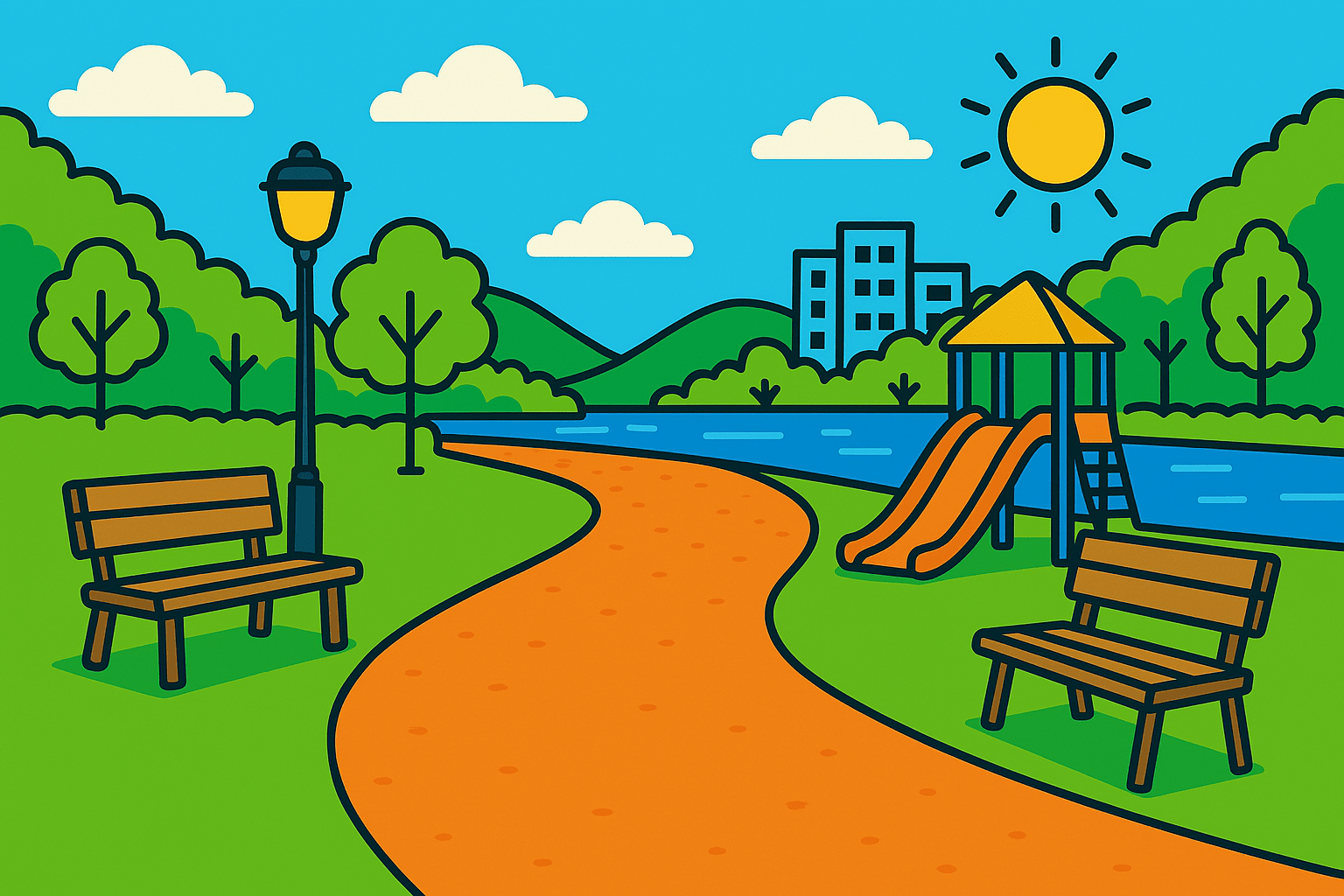
“ごみを出さないまちづくり”という言葉を耳にすることが増えました。しかし、ただ分別を徹底し、家庭ごみの量を減らすだけでは、本当の意味での循環型社会は実現しません。地域が本気で「持続可能なまちづくり」を目指すなら、もっと大きな視点、つまり“公共工事”の現場からの変革が必要です。
実は、地方自治体が発注する公共工事では、非常に多くの資材が使われ、その過程で大量の廃棄物が発生しています。道路整備、河川護岸、学校の建て替え…。そのすべてに共通するのが、「資材の選択」という工程です。そして今、その選択に「リサイクル材を使う」という視点が加わり始めています。
たとえば、再生砕石(リサイクル骨材)は、解体された建物やコンクリート構造物から得られるがれきを破砕・再処理してつくられた資材であり、道路の路盤材や埋戻し材としての使用に適しています。多くの自治体では、再生資材の使用率を高める方針を策定し、入札時の加点評価制度や仕様書への明記といった形で実効性を持たせています。
ある地方都市では、市が主導する公共工事で再生砕石の使用率を90%以上に設定。地元の解体業者・再資源化業者との連携体制を構築し、建設副産物の地産地消を実現しています。これは、輸送コストやCO₂排出の削減だけでなく、地域経済の循環にも寄与しています。
また、再生プラスチックを活用したベンチ、舗装ブロック、仮設フェンスなど、目に見える形でリサイクル資材が使われていると、住民の意識も変わってきます。「ごみがまちをつくっている」という事実が、地域の誇りにさえなるのです。
こうした取り組みは、単なるコスト削減ではありません。限りある資源を循環させ、未来世代に負荷を残さない“公共の責任”として、リサイクル資材の活用は今や重要な選択肢なのです。
自治体は、地域の価値観をかたちにする存在です。もし“持続可能性”が本気で求められるなら、その理念を、公共事業という目に見える場で示すことが、なによりも効果的です。公共工事は未来への投資――だからこそ、その材料もまた、未来につながるものであってほしい。
リサイクル資材の使用は、自治体ができる最も具体的な環境アクションの一つです。
まちの未来は、アスファルトの下から始まっているのです。
